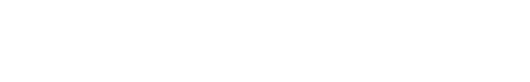Blog
ARCHIVES
2025.8.11
【鼻整形】感染リスクはいつまで続く?原因や予防法も解説

鼻整形を考えている方の中には、「術後の感染リスクはいつまで続くのか」と不安を感じている方もいるでしょう。
発症率は1%未満と低めですが、感染すると鼻の形が変わってしまったり、再手術が必要になるケースもあります。
そこで本記事では、鼻整形後に起こりうる感染の原因や症状、リスクを減らすための予防法について解説します。
目次
鼻整形の感染リスクはいつまで?術後2週間はリスクが高い

鼻整形後の感染リスクは、術後2週間が最も高くなります。
手術で切開した傷口が塞がっておらず、細菌が侵入しやすい状態だからです。
傷口が治癒すれば、感染リスクは低下しますが、完全にゼロになるわけではないため、ケアを怠らないようにしましょう。
異物(プロテーゼなど)を入れている場合の感染リスクは永年
プロテーゼなどの異物を挿入している場合、感染のリスクは何年経ってもゼロにはなりません。
異物には血流がないため、細菌が付着しても、血流に乗って運ばれる免疫細胞が細菌を排除できないからです。
そのため、異物が体内にある限り、ごくわずかではありますが、感染のリスクは継続します。
プロテーゼを挿入する際は、本当に必要な施術かよく医師と話し合って決めるのがおすすめです。
鼻整形の感染確率はどれくらい?1%以下の臨床研究データあり
海外の医師が16年間で行った鼻整形2630例を調査した結果、術後に感染がみられたのは全体の0.84%でした。
そのうちの大半は再手術後に起きたもので、初回手術の0.19%に対し、再手術では3.63%と約19倍も高い感染率が報告されています。
| 手術の種類・条件 | 症例数 | 感染率 |
| 鼻整形 全体 (初回+再手術) | 2630 | 0.84% |
| 初回手術 | 2134 | 0.19% |
| 再手術 | 496 | 3.63% |
再手術は、一度切開した部分にもう一度手を加えるため、前の手術でできた硬くなった組織やくっついた部分を丁寧に処理する必要があります。
手術時間や範囲が広がる影響で、血流や組織の回復力が落ち、感染を防ぐ力も弱まりやすくなるのです。
そのため、失敗や再手術のリスクを抑えられる経験豊富な医師を、はじめから選ぶのが良いでしょう。
鼻整形の感染リスクが高まる原因4つ

鼻整形で感染が起こるのは、手術中や術後に細菌が傷口から入り込み、体内で増えることが原因です。
さらに、術後の生活習慣や体調などが重なることで、感染の可能性は高まります。
事前に対策を取るためにも、まずは感染が起こる原因を理解しておきましょう。
傷口から細菌が侵入した
鼻整形後は、傷口がふさがるまでの間、切開部分が細菌の侵入口となり、体内に入りやすい状態が続きます。
鼻の中や皮膚に常在する菌だけでなく、手指に付着した雑菌が入り込むことも。
清潔ではない手で傷口に触れる、処方された抗生剤を飲まないといった行動は感染の原因になりやすいため、できるだけ避けましょう。
挿入した異物から感染した
鼻整形で使われるプロテーゼや糸などの人工物は、血流が通わないため感染しやすいのが特徴です。
血流がある組織では、血液に乗って細菌と戦う細胞が運ばれ、増殖を抑えてくれます。
しかし人工物には血管がないため、細胞が届かず、付着した細菌が増えやすい状態に。
そのため、体の一部から採った耳介軟骨や肋軟骨などの血流のある組織を使う場合よりも、感染のリスクが高くなるのです。
腫れや血流による影響を受けた
鼻整形後は、血流が滞ることで感染しやすい状態になります。
強い腫れや血腫ができると、組織に十分な血液が行き渡りません。
細菌と戦う細胞が運ばれにくくなるため、細菌への抵抗力が低下するのです。
さらに喫煙習慣があると、ニコチンの作用で血流が悪化し、感染リスクが上がることもあります。
術後の回復が遅れ、感染リスクを高める要因となるため、手術後は喫煙をはじめ、血流を阻害する行動は控えましょう。
ダウンタイム中の指示を守らなかった
ダウンタイム中に医師の指示を守らないと、傷の治りが遅れ、感染のリスクが高まります。
指示には、血流を保つための生活制限や、細菌の侵入を防ぐための過ごし方などが含まれますよ。
ケアを怠ると、免疫が十分に働かず、細菌が繁殖しやすい環境になってしまうため、医師の指示は最後まで徹底しましょう。
鼻整形の感染リスクを下げるための5つのコツ

鼻整形後の感染は、医師の技術力や、術後の過ごし方によっても左右されます。
一度感染すると、追加の処置や再手術が必要になる場合もあり、心身ともに大きな負担になることも。
だからこそ、事前に感染を防ぐためのコツを知っておきましょう。
鼻整形の施術経験が豊富な医師を選ぶ
鼻整形の感染リスクを下げるには、施術経験が豊富な医師を選ぶことも大切です。
経験の浅い医師が行うと、手術時間が長引きやすいため、細菌が侵入する機会が増えてしまいます。
また、慣れない操作により、組織へのダメージや出血が多くなり、局所の血流が悪化することも。
一方で、経験を積んだ医師は、必要なだけの切開と短時間の手術で組織への負担を抑えられるため、感染リスクを軽減できるでしょう。
▼経験豊富な医師の特徴
・鼻整形の症例数が多い
・SNSに症例写真を多く形成している
・学会や論文での発表実績がある
・形成外科専門医などの資格を持つ
(日本形成外科学会認定)
・修正手術にも対応している
また、万が一のトラブルにも対応してもらえるよう、相談しやすい雰囲気かどうかも重要です。
カウンセリングで直接話し、話しやすいと感じる医師を選びましょう。
傷口は触らず清潔に保つ
感染を防ぐためには、まず手や指を清潔に保ち、頻繁に患部に触れないことが大切です。
鼻整形後のダウンタイム中は、傷口が細菌に感染しやすいため、衛生的な環境を心がけましょう。
▼清潔を保つためのポイント
・手洗いを徹底する
・個包装の綿棒を使い、鼻周辺を清潔にする
・常に清潔なマスクを使用する
・拭き取りタイプの洗顔シートなどで顔を清潔に保つ
術前後1〜3か月は禁煙を心がける
感染リスクを下げるためにも、術前から禁煙を開始し、術後も少なくとも3か月は継続しましょう。
喫煙によって体内に取り込まれるニコチンは血管を収縮させ、手術部位の血流を悪化させます。
血流が滞ると切開部分に必要な酸素や栄養が届きにくくなると、傷の治りが遅れるだけでなく免疫機能も低下し、細菌が侵入しやすくなることも。
なお、禁煙は術後だけでなく、手術前から始めましょう。
手術前から禁煙することで、血流の改善が見込め、手術当日には回復に適した状態を整えられますよ。
規則正しい生活をし免疫力を保つ
鼻整形後の感染リスクを下げるためには、免疫力を維持できる生活習慣を整えましょう。
特にダウンタイム中は、睡眠・ストレス管理・栄養摂取の3つをバランス良く整えることが重要です。
十分な睡眠と休養をとる
鼻整形後は、まずしっかりと眠ることや休息を取ることを心がけましょう。
7〜8時間の睡眠は成長ホルモンの分泌を促し、傷ついた組織の修復を助けます。
さらに、睡眠中は免疫に関わるサイトカインが多く作られるため、炎症を抑えながら回復を促し、細菌への抵抗力も高めてくれますよ。
ストレスを溜めない
強いストレスは自律神経を乱し、免疫細胞の働きを弱めるため、アロマや深呼吸など、自分に合った方法で心を落ち着けましょう。
心身がリラックスすると副交感神経が優位になり、血流が改善します。
血の巡りが良くなることで、回復に必要な酸素や栄養が患部まで届きやすくなりますよ。
栄養バランスの良い食事
食事は、傷の修復に欠かせないたんぱく質や、免疫機能を支えるビタミンC・E、亜鉛を意識して摂取しましょう。
一方で、糖質や脂質に偏った食事は炎症を長引かせる物質を増やし、免疫機能を乱す原因になります。
我慢のしすぎはストレスにつながるため、嗜好品も取り入れつつ、全体のバランスを意識した食事が重要です。
定期検診は必ず受ける
感染兆候にいち早く気づくためにも、定期的に医師の診察を受けましょう。
クリニックによっては、術後1週間・1か月・3か月・半年など、段階的なフォローアップを設けている場合があります。
| 時期 | 診察内容 | 目的 |
| 3日目 | 固定抜去 | 固定具を外し、鼻の状態を確認する |
| 1週間 | 抜糸 | 傷口の回復具合を確認し、抜糸する |
| 1か月後 | 経過観察 | 腫れや赤みの残り具合など、鼻の状態を確認する |
| 3か月後 | 仕上がり確認 | 鼻の形や左右差、異常の有無を評価する |
| 6か月後 | 長期経過確認 | 傷跡や鼻の状態を確認する |
定められたスケジュールを守ることで、異常が見つかった際にもすぐに対応でき、回復を妨げるリスクを減らせるでしょう。
鼻整形で感染したらどうなる?感染兆候(症状)を解説
鼻整形後に感染すると、赤みや強い痛み、熱っぽさなどを伴います。
●患部の赤みや熱感
手術部位の皮膚が周囲より赤く腫れ、触れると熱を帯びている状態です。
局所的な炎症や、感染の初期サインの可能性があります。
●強い痛みや腫れが長く続く
術後の痛みや腫れは1週間ほどで落ち着きますが、感染すると痛みが強まったり、腫れが引かずに悪化することがあります。
●膿や分泌物が出る
傷口や鼻孔から黄白色の膿が出る場合は細菌感染が疑われます。
傷口がジクジクして治らない、においを伴う場合も注意が必要です。
●発熱や全身のだるさ
感染が進行すると38℃以上の発熱や全身の倦怠感が現れることがあります。
局所だけでなく全身症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
症状がいくつも重なるほど、感染の可能性は高くなります。
傷口の赤みや腫れが続き、痛みや膿が出るなど明らかな異常があれば、すぐに手術を受けたクリニックへ連絡しましょう。
放置すると、皮膚が壊死したり、皮膚が破れてプロテーゼが露出する危険性もありますよ。
鼻整形で感染したら治る?治療法を解説

鼻整形後に感染してしまった場合でも、早期に正しい治療を受ければ回復は十分可能です。
▼感染後の治療法
| 治療法 | 内容 |
| 抗生剤の投与 | 軽度の感染であれば、内服薬や点滴で炎症を抑える |
| 膿の排出 | 切開して膿を除去し、細菌の温床を取り除く |
| 異物の除去と洗浄 | 感染がプロテーゼや移植軟骨に及んでいる場合に実施 |
再手術は炎症や瘢痕が完全に落ち着くまで、6〜12か月ほど待つ必要があります。
時期を早めると仕上がりや組織の安定性に悪影響を及ぼす可能性があるため、炎症が落ち着くまでの間はケアと経過観察を継続しましょう。
鼻整形の感染リスクはいつまで?に関するQ&A
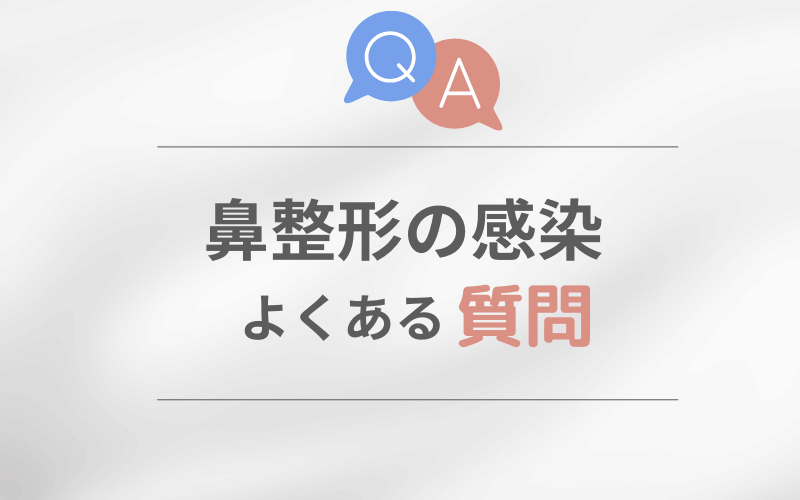
鼻整形の感染は何ヶ月後?
鼻整形後の感染は、術後2週間前後がピークで、1か月以内に起こることが多く、時間の経過とともにリスクは低下していきます。
ただし、プロテーゼなどの異物を挿入している場合は、長期間経っても完全に感染リスクがなくなるわけではありません。
術後しばらく経ってからでも腫れや赤み、痛みが続く場合は、早めに医師へ相談しましょう。
鼻整形で感染した兆候は?
鼻整形後に感染すると、強い赤みや痛み、膿が出るなどの症状が現れることがあります。
▼感染が疑われる主な兆候
・腫れや赤みが悪化している
・熱感や強い痛みが続く
・患部から膿や血がにじみ出る
・発熱や全身のだるさを伴う
感染を放置すると、炎症が広がって組織の壊死や変形を招く恐れも。
症状が見られた場合は、市販薬や自己判断で様子を見ず、できるだけ早く手術を受けたクリニックや医師に連絡しましょう。
鼻の糸(スレッド)は感染する?
鼻に糸を挿入する施術は、稀ではありますが、感染する可能性があります。
施術を受けるなら、術後は清潔な状態を保ち、少しでも異常を感じたら早めに医師へ相談しましょう。
鼻整形の感染リスクに配慮された施術ならXクリニックがおすすめ
鼻整形の感染リスクは、術後2週間ほどが最も高く、その後は徐々に落ち着いていきます。
ただし、プロテーゼを入れている場合は、時間が経ってもリスクが完全にゼロになることはありません。
感染の背景には、術後の衛生管理不足や、手術時間の長さなども関係します。
鼻整形を受ける際は、経験豊富な医師を選ぶことと、丁寧な術後ケアを心がけましょう。
Xクリニックでは、形成外科専門医が手術を担当し、術中はガウンや滅菌器具の使用など徹底した感染対策を行っています。
さらに、術後も経過観察や必要に応じた処置を行うフォローアップ体制を整えており、気になる症状があればすぐに相談できる環境です。
鼻整形の感染リスクに配慮された施術を希望される方は、ぜひ当院へご相談ください。
◉LINEでのご予約はこちらから
◉お電話での予約は、お近くの院にご連絡ください。
恵比寿院:03-5734-1921
銀座院:03-6228-6120
大阪院:06-6476-8424
福岡天神院:092-406-7749
名古屋院:052-684-9790